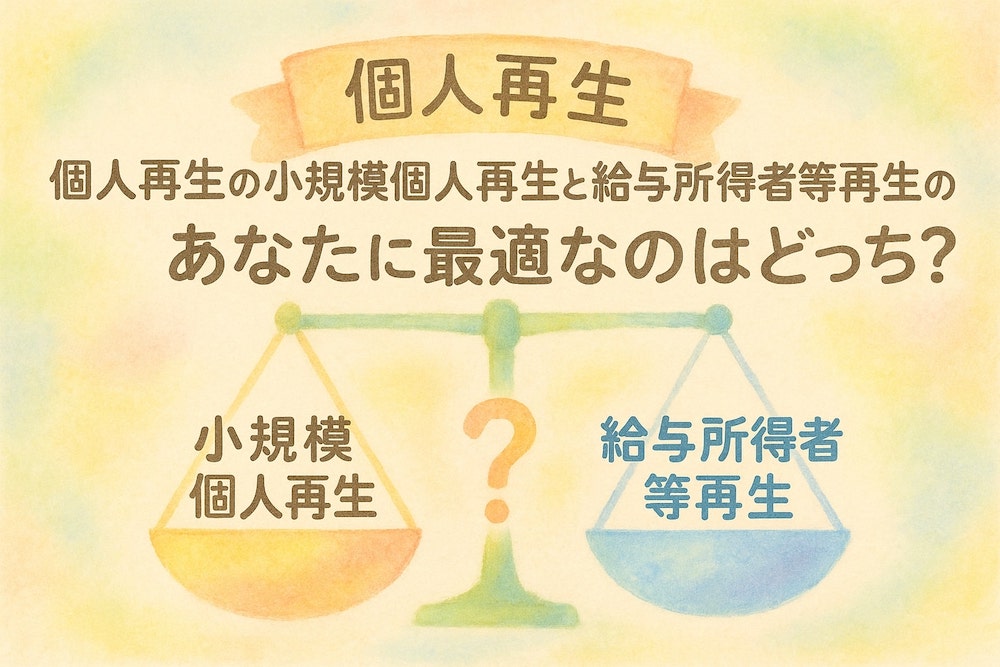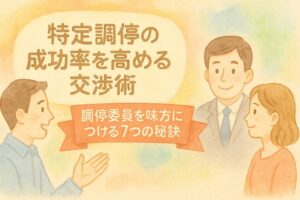「この家だけは、子どものために手放したくない…」
離婚後に発覚した元夫の借金と、滞納し始めた住宅ローンに追われ、夜も眠れなかった3年前の私。藁にもすがる思いで訪れた法律事務所で、弁護士さんから「個人再生には2種類あります」と告げられた瞬間、頭が真っ白になったのを今でも覚えています。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」。
ただでさえ難しい法律の話なのに、さらに選択肢があるなんて…。当時の私には、その違いが全く分かりませんでした。
この記事では、かつての私と同じように悩んでいるあなたのために、個人再生の2つの手続きの違いを、私の体験談を交えながら分かりやすく解説していきます。
【この記事の結論】小規模個人再生と給与所得者等再生の選択ポイント
- 原則は「小規模個人再生」を選ぶ
ほとんどのケース(利用者の9割以上)で、こちらの方が返済額を低く抑えられる可能性が高いため、第一候補となります。パートや自営業者など、働き方を問わず利用できるのも特徴です。 - 「給与所得者等再生」を選ぶ特別なケース
「債権者に反対される可能性が高い」「過去7年以内に自己破産などをしている」といった特別な事情がある場合に検討する手続きです。債権者の同意が不要という大きなメリットがあります。 - 一番の違いは「返済額」と「債権者の同意」
小規模個人再生は「債権者の同意」が必要ですが、返済額は低めになる傾向があります。一方、給与所得者等再生は「債権者の同意」が不要な代わりに、「可処分所得」も計算に加わるため返済額が高めになる傾向があります。
本文では、これらのポイントや住宅ローン特則との関係について、さらに詳しく解説します。
【体験談】小規模個人再生と給与所得者等再生、私が悩んで選んだのはこっち
法律事務所で初めて聞く「小規模」と「給与所得者等」という言葉
弁護士さんの説明を聞きながら、私の頭の中は「?」でいっぱいでした。「ショウキボ…?」「キュウヨショトクシャトウ…?」まるで外国語のように聞こえて、正直、話の半分も理解できていなかったかもしれません。
ただでさえ借金のことで頭がいっぱいなのに、さらに難しい選択を迫られているようで、不安で胸が張り裂けそうでした。「私なんかに、決められるわけがない…」と。あなたも今、そう感じていませんか?でも、大丈夫。一つひとつ整理していけば、必ず道は見えてきます。
私が「小規模個人再生」を選んだ一番の理由
弁護士さんと何度も話し合い、最終的に私が選んだのは「小規模個人再生」でした。
一番の決め手は、「毎月の返済額を少しでも抑えて、子どもの教育費を確保したかった」からです。シングルマザーの私にとって、娘との生活を守ることが何よりも大切でした。将来の学費や、やりたいと言った習い事を諦めさせたくない。その一心だったんです。
弁護士さんから「佐藤さんの場合、小規模個人再生の方が返済額を低くできる可能性が高いですよ」と聞き、迷いは消えました。この選択が、今の穏やかな生活に繋がっています。
小規模個人再生と給与所得者等再生の基本的な違いとは?
では、この2つの手続き、一体何が違うのでしょうか?難しく考えずに、まずはこんなイメージを持ってみてください。
原則は「小規模個人再生」:パートや自営業者も利用可能
こちらは「個人再生の基本形」です。実は、個人再生をする方の9割以上が、この小規模個人再生を選んでいます。正社員だけでなく、パートやアルバイト、個人事業主(自営業)の方でも利用できる、間口の広い手続きなんです。
家計で言えば、毎日の基本となる「食費」みたいなものですね。ほとんどの人がまずここから考える、というイメージです。
特別版は「給与所得者等再生」:安定収入のある方向け
こちらは、その名の通り「お給料が安定している方向けの、ちょっと特別なプラン」です。毎月のお給料がほとんど変わらない会社員や公務員の方などが対象になります。
基本の食費に加えて、特別な日に少し豪華にする「外食費」のようなイメージでしょうか。全員が必要なわけではなく、特定の状況で選ばれる選択肢なんです。
【比較表】小規模個人再生と給与所得者等再生の5つの違いを徹底解説
言葉だけだと分かりにくいので、2つの違いを簡単な比較表にまとめてみました。ポイントはたったの5つです!
比較ポイントは5つだけ!
| 比較ポイント | 小規模個人再生(原則) | 給与所得者等再生(特別版) | 佐藤さんのひとこと解説 |
|---|---|---|---|
| 利用条件 | 継続的な収入があればOK | 安定した給与収入が必要 | パートの私でも小規模なら大丈夫でした!働き方に関わらず選べるのが嬉しいですよね。 |
| 返済額の決まり方 | 借金額や財産で決まる(低めになりがち) | +可処分所得も考慮(高めになりがち) | ここが一番の分かれ道。少しでも返済を抑えたいなら小規模が断然有利です。 |
| 債権者の同意 | 必要(でも反対は稀) | 不要 | 「貸してくれた人の半数が反対したらダメ」と聞き不安でしたが、実際はほとんどないそうです。 |
| 利用できる人 | 全員(自営業、パートも可) | 会社員・公務員など | 働き方が多様な今、多くの方が小規模を選ぶのは自然なことかもしれませんね。 |
| 過去の利用制限 | なし | 過去7年以内に利用歴があるとNG | 再チャレンジのしやすさも違います。万が一の時を考えると、大きな違いですよね。 |
小規模個人再生と給与所得者等再生、どっちを選ぶ?判断基準を3つのポイントで解説
表を見ても「じゃあ、私はどっち?」と迷ってしまいますよね。大丈夫です。あなたがどちらを選ぶべきか、3つのチェックポイントで一緒に考えていきましょう。
チェック1:あなたの収入は安定的?変動がある?
給与所得者等再生は、「収入の変動幅が小さいこと」が条件になります。そのため、ボーナスや残業代で月々のお給料が大きく変わる方や、歩合制のお仕事の方は、条件を満たさない可能性があります。
私の場合はアパレル店長でしたが、繁忙期と閑散期で残業代が違いました。そんな風に収入に波がある方は、条件が緩やかな「小規模個人再生」の方が安心かもしれません。
チェック2:返済額は少しでも低く抑えたい?
ここが一番大切なポイントです。先ほどの表にもあったように、給与所得者等再生は返済額が高くなる可能性があります。
その理由は「可処分所得」という少し難しい計算が入るためです。簡単に言うと「あなたのお給料の手取りから、税金や社会保険料、法律で定められた最低限の生活費を引いた残り」のこと。家計簿で最後に残る「自由に使えるお金」みたいなイメージですね。
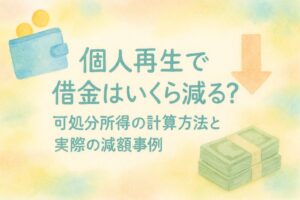
給与所得者等再生では、この「可処分所得」の2年分以上を返済しなくてはならない、というルールが追加されるんです。扶養家族が少ない方などはこの金額が大きくなりやすく、結果的に小規模個人再生よりも返済総額が増えてしまうケースが多くあります。
私のように「少しでも返済額を抑えて、生活や子どものためにお金を残したい」と考えるなら、まずは小規模個人再生を検討するのが基本になります。
チェック3:債権者に反対されそうな心当たりはある?
「じゃあ、給与所得者等再生を選ぶメリットって何?」と思いますよね。
その唯一ともいえる大きなメリットが「債権者の同意が不要」なことです。小規模個人再生では、再生計画に債権者の半数以上(または借金額の半分以上)が反対すると、手続きを進められません。(実際に反対されることは滅多にありませんが…)
もし、特定の金融機関からだけ突出して多く借りている、過去に返済で大きなトラブルがあったなど、債権者に反対されそうな特別な事情がある場合は、同意が不要な給与所得者等再生を選ぶ価値が出てきます。
住宅ローン特則の利用|小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
「家だけは手放したくない…」これは、個人再生を考える多くの方、特に子育て中のママ・パパの切実な願いだと思います。
結論:住宅ローン特則はどちらの手続きでも使えます!
まず、安心してくださいね。
持ち家を守りながら借金を整理できる「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度は、小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらを選んでも利用できます。
この点において、どちらが有利・不利ということはありません。「家を守りたいから、こっちの手続きを選ばないと!」と焦る必要はないので、落ち着いて自分に合った手続きを選びましょう。

私が家を守るために気を付けたこと【体験談】
住宅ローン特則を使う上で、私が弁護士さんからアドバイスされ、徹底していたことがあります。それは、「住宅ローンだけは、絶対に支払いを止めない・遅れない」ということです。
他のカードローンなどの返済は弁護士さんに依頼した時点でストップしますが、住宅ローンだけは今まで通り払い続ける必要があります。私は不安で、カレンダーの支払い日に真っ赤な丸をつけて、毎月何度も確認していました。この家で娘と笑い合う未来を守るためだと思うと、不思議と頑張れたんです。
よくある質問(FAQ)
最後に、よくいただく質問にお答えしますね。
Q: パートやアルバイトでも個人再生できますか?
A: はい、できますよ。実際にパート勤務だった私も「小規模個人再生」を利用しました。大切なのは、毎月返済していけるだけの継続的な収入があるかどうかです。収入が不安定な方ほど、返済額が低く抑えられる可能性のある小規模個人再生が向いていることが多いです。
Q: 小規模個人再生で、債権者に反対されたらどうなりますか?
A: もし債権者の半数以上、または借金額の半分以上を占める債権者が反対した場合、小規模個人再生は認められません。ただ、弁護士さん曰く、実際には反対されるケースは本当に稀だそうです。もし反対される可能性が高い特別な事情がある場合は、債権者の同意が不要な「給与所得者等再生」を検討することになります。
Q: 給与所得者等再生の返済額が高くなるのはなぜですか?
A: 「可処分所得の2年分」という返済額の基準が追加されるためです。これは、あなたの収入から税金や最低限の生活費を引いた金額(自由に使えるお金)の2年分は返済してください、というルールなんです。扶養家族が少ない方などは、この金額が大きくなりやすい傾向があります。
Q: 結局、ほとんどの人が小規模個人再生を選ぶって本当ですか?
A: はい、その通りです。実務では9割以上の方が小規模個人再生を選んでいると言われています。理由は、利用条件が緩やかで、何より返済額を低く抑えられる可能性が高いからです。給与所得者等再生は、債権者の反対が予想されるなど、ごく限られたケースで選ばれる特別な手続きと考えると分かりやすいですよ。
Q: シングルマザーが個人再生する上で、特に注意すべきことはありますか?
A: 養育費の扱いや、児童扶養手当などの公的支援が収入としてどう見なされるか、という点です。これらは再生計画を立てる上で非常に重要になります。特に養育費の支払い義務は個人再生をしてもなくなりません。また、手続き中は精神的にも不安定になりがちなので、一人で抱え込まず、信頼できる専門家や支援団体に相談することが大切です。「あなたは一人じゃない」ということを忘れないでくださいね。
まとめ
ここまで、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについてお話ししてきました。
一番大きな違いは、「返済額の決まり方」と「債権者の同意が必要かどうか」の2点です。そして、ほとんどの人が返済額を抑えられる「小規模個人再生」を選んでいる、ということを覚えておいてください。
どちらの手続きが最適かは、あなたの収入の状況や借入先との関係によって全く違います。だからこそ、一人で悩まずに、法律のプロである弁護士さんや司法書士さんと一緒に考えることが何よりも大切なんです。
かつての私のように、今あなたは出口の見えない暗いトンネルの中にいるように感じているかもしれません。でも、正しい知識を身につけて、勇気を出して専門家に相談するという一歩を踏み出せば、必ず光は見えてきます。
あなたの状況に最適な方法を専門家と一緒に見つけませんか?多くの法律事務所では無料相談を実施しています。まずは電話一本、メール一通から、あなたの新しい人生の一歩を始めてみましょう。公的な相談窓口である「法テラス」に問い合わせてみるのも良い方法ですよ。
あなたの未来が、少しでも明るいものになるよう、心から応援しています。