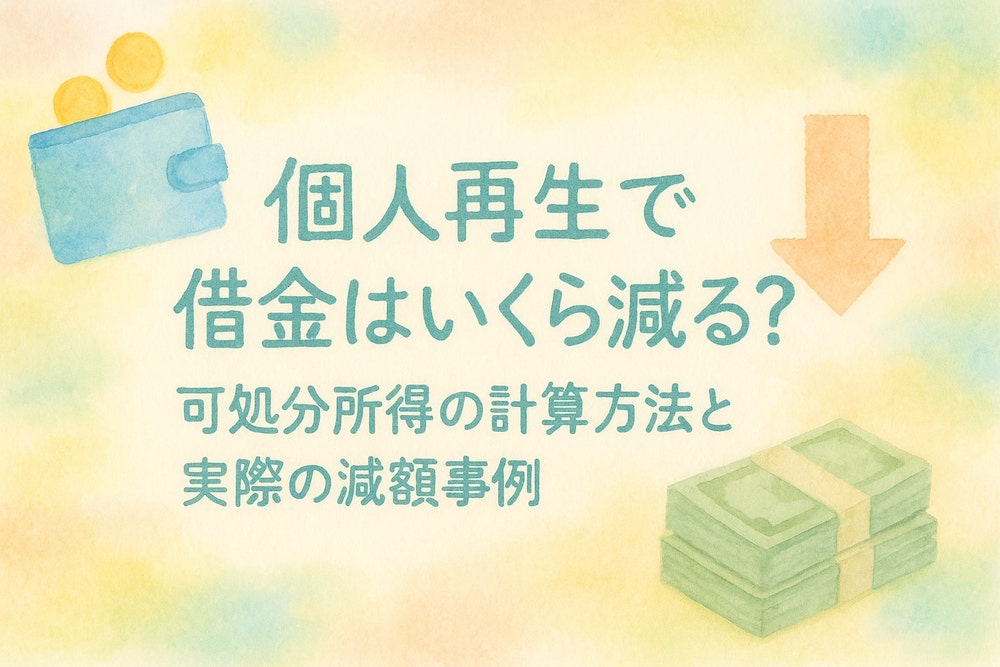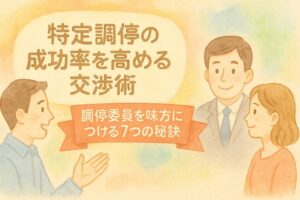「この借金、一体いくらまで減らせるんだろう…?」
3年前、離婚後に発覚した元夫の借金400万円を抱え、シングルマザーとして途方に暮れていた私が、毎日のように考えていたことです。息子の寝顔を見るたび、「この子の将来を、私が守れるんだろうか」と胸が張り裂けそうでした。
この記事では、個人再生で借金がいくら減るのかを具体的に知る方法をお伝えします。最後まで読めば、あなたも「私の借金なら○○万円まで減らせる!」と希望の光が見えるはずです。
結論から言うと、個人再生での返済額は「3つのものさし」で決まり、「可処分所得」の計算さえマスターすれば、あなたの未来が数字で見えてきます。
400万円の借金を大幅に減額し、家を守った私が、家計簿をつけるような感覚で分かりやすく解説します。

私も通った道だからわかる!そもそも個人再生ってどんな手続き?
「自己破産」とは違う、家や車を残せる可能性がある再出発の道
「債務整理」と聞くと、「自己破産」を思い浮かべて、家も車も何もかも失ってしまう…そんな風に考えていませんか?実は私もそうでした。でも、個人再生は違うんです。
一番大きな違いは、条件を満たせば財産を手放さずに借金を大幅に減額できること。私にとって何より大きかったのは、「住宅ローン特則」という制度を使って、今住んでいる家を守れたことでした。
「ママ、この家に住み続けられるの?」と不安そうに聞いてきた息子の顔が、今でも忘れられません。その時、「大丈夫、絶対にこの家で暮らし続けるからね」と約束できたのは、個人再生という選択肢があったからです。
「全部失うわけじゃない」という希望が、前に進むための大きな力になりました。
私が個人再生を選んだ理由と、手続き後の生活の変化
私には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの選択肢がありました。その中で個人再生を選んだのは、
- どうしても息子との思い出が詰まった家を手放したくなかった(住宅ローンがあった)
- 借金の総額が大きく、毎月の返済額を減らすだけでは解決が難しかった
という2つの理由が大きかったです。
手続きを終えた今、生活は本当に変わりました。一番は、精神的なプレッシャーからの解放です。
以前は常に返済のことで頭がいっぱいで、督促の電話におびえる毎日。でも今は、借金の返済計画がきちんと立ったことで、心穏やかに息子と向き合う時間が増えました。
「お金がないから」と我慢させていたことにも、少しずつ応えてあげられるようになったんです。

あなたの借金はいくらに?減額が決まる「3つのものさし」
では、実際に個人再生で返済額がいくらになるのか、見ていきましょう。
これは、主に3つの「ものさし」で測られ、その中で一番金額が高いものが、あなたの実際の返済額になります。
ものさし①:借金の総額で決まる「最低弁済額」
これは、借金の総額に応じて法律で「最低でもこれだけは返済してくださいね」と決められている金額のこと。多くの人がこの基準で返済額が決まるので、一番の目安になります。
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 減額なし(全額) |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円未満 | 借金額の10分の1 |
例えば、私のように借金が400万円だった場合、このものさしでは100万円になります。もし700万円の借金があれば、5分の1の140万円ですね。これだけでも、かなり楽になるのが分かりますよね。
ものさし②:持っている財産の価値で決まる「清算価値」
これは、「もしあなたが自己破産をしていたら、これだけの財産は手放すことになり、債権者に分配されたはず」という考え方に基づく金額です。個人再生では、少なくともその金額以上は返済しましょう、というルールがあるんです。
対象になるのは、
- 預貯金
- 解約したら戻ってくる生命保険金(解約返戻金)
- 20万円以上の価値がある車
- 不動産
などです。
私の場合は、預貯金はほとんどなく、乗っていた車も古くて価値がなかったので、清算価値は50万円ほどでした。
ものさし③:収入から計算する「可処分所得」(給与所得者等再生の場合)
これが一番ややこしいのですが、簡単に言うと「あなたの手取り収入から、法律で定められた最低限の生活費を引いた残り」のことです。
このものさしは、主に会社員など安定した収入がある人が利用する「給与所得者等再生」という手続きで使われます。少し複雑なので、次の章で私の家計簿を例に、一緒に計算してみましょう!
【一番の壁】可処分所得の計算を、シングルマザーの家計簿でやってみよう!
ここがこの記事の一番大切なポイントです。多くの人が「分からない!」と諦めてしまう可処分所得の計算ですが、ステップごとに分解すれば大丈夫。
当時の私(35歳、小学生の息子と二人暮らし、関東の市在住)をモデルに、一緒に計算の流れを見ていきましょう。
ステップ1:まずは「収入」を全部書き出してみよう
まず、年収を計算します。これは手取りではなく、税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」です。源泉徴収票の「支払金額」の欄を見れば分かります。
そして、ここが注意点!実は、児童扶養手当などの公的支援も収入に含まれるんです。私も最初は「え、これも収入なの!?」って驚きました。
- 私の年収(総支給額):360万円
- 児童扶養手当(年額):約48万円
- 年収合計:408万円
ステップ2:次に「引かれるもの(税金・社会保険料)」を確認
次に、年収から天引きされている所得税、住民税、社会保険料(健康保険、厚生年金など)を合計します。これは給与明細や課税証明書で確認できます。
- 私の税金・社会保険料の合計(年額):約70万円
ステップ3:最後に「最低生活費」を計算します
ここが一番複雑です。これは実際の家賃や光熱費ではなく、国が「この家族構成でこの地域なら、最低限このくらいの生活費がかかるよね」と定めた基準額です。家族の年齢や人数、住んでいる地域(1級地~3級地)などで細かく決まっています。
私のケース(35歳本人+小学生の子供1人、関東の市在住)で、弁護士さんが計算してくれた金額は、おおよそ以下のようになりました。
私の最低生活費(年額):約140万円
- (内訳のイメージ:個人の生活費、世帯の生活費、住居費、冬の暖房費など、色々な項目を足して計算します)
計算結果:「可処分所得の2年分」が返済額の候補に
さあ、これで計算できます。
(ステップ1:収入) – (ステップ2:税金等) – (ステップ3:最低生活費) = 1年分の可処分所得
私の場合は…
408万円 – 70万円 – 140万円 = 198万円
これが1年分の可処分所得です。そして「給与所得者等再生」では、この2年分が返済額の基準になります。
198万円 × 2年 = 396万円
…あれ?借金400万円なのに、返済額が396万円?ほとんど減らないじゃない!と驚きますよね。そうなんです。この可処分所得の基準が高額になってしまうことがあるのが、この手続きの難しいところなんです。
【実録】私や周りの人はこうやって借金を減らしました!減額事例3選
では、私の返済額は結局どうなったのでしょうか?3つの「ものさし」を比べてみましょう。
事例1:私の場合(住宅ローンあり・400万円の借金)
- ものさし① 最低弁済額:借金400万円 → 100万円
- ものさし② 清算価値:預貯金や車の価値 → 50万円
- ものさし③ 可処分所得の2年分:計算したら → 396万円 ※
※先ほどの計算は給与所得者等再生の場合です。実は、私は弁護士さんと相談し、多くの人が選ぶ「小規模個人再生」という手続きを選びました。この手続きでは、可処分所得の計算は原則不要で、「最低弁済額」と「清算価値」のどちらか高い方が返済額になります。(ただし、債権者の反対が一定数あると認められません)
その結果、私の返済額は、100万円と50万円を比べて高い方の「100万円」になりました。
この100万円を原則3年(36回)で分割返済していくことになったのです。
月々の返済額は約2万8千円。もちろん、これとは別に住宅ローンは払い続けますが、以前の返済額に比べれば、天と地ほどの差でした。
事例2:Aさん(40代・会社員・独身)の場合
- 借金総額:700万円
- ものさし① 最低弁済額:140万円(5分の1)
- ものさし② 清算価値:300万円(価値の高い車と、解約返戻金が多い保険を持っていた)
Aさんの場合、最低弁済額(140万円)よりも清算価値(300万円)の方が高かったため、返済額は300万円になりました。持っている財産が多いと、減額幅が少なくなるケースもあるんですね。
事例3:Bさん(30代・パート主婦・子供2人)の場合
- 夫の収入はあるが、自身のパート代で作った借金500万円で個人再生
- ものさし① 最低弁済額:100万円
- ものさし③ 可処分所得の2年分:低額(子供2人を扶養しているため、最低生活費が高く計算された)
Bさんは、ご主人の収入が高かったため「給与所得者等再生」を選びましたが、扶養家族が多いことで最低生活費が高く計算され、可処分所得がとても低くなりました。
そのため、3つのものさしの中で一番高い「最低弁済額」である100万円での再生計画が認められました。
よくある質問(FAQ)
Q: 可処分所得を計算したら、最低弁済額よりかなり高くなりました。どうなりますか?
A: その場合、残念ながら高い方の「可処分所得の2年分」が返済額の基準になる可能性があります。そのため、多くの会社員の方は、私のように、より有利な条件になることが多い「小規模個人再生」(可処分所得の計算が原則不要)を選択できないか、弁護士さんと相談することになります。
Q: パートやアルバイトでも個人再生できますか?
A: はい、できます!大切なのは「継続して収入を得る見込みがあること」です。私も正社員ではなく、アパレル店長としてのパート収入でしたが、裁判所に認めてもらえました。収入が不安定な場合は、家計の状況を丁寧に説明することが重要になります。
Q: 住宅ローン以外の借金だけ減らせるって本当ですか?
A: 本当です。「住宅ローン特則」という制度を使えば、住宅ローンは今まで通り(あるいは計画を見直して)返済を続け、それ以外のカードローンやキャッシングなどの借金だけを減額することができます。私もこの制度のおかげで、息子の学校や友達関係を変えずに済みました。
Q: 計算が複雑すぎて自分ではできません。どうすればいいですか?
A: 当然です!私も最初はちんぷんかんぷんでした。この記事でお伝えしたのは、あくまで計算のイメージです。正確な金額は、弁護士さんや司法書士さんといった専門家が、あなたの状況に合わせて資料を元にきっちり計算してくれます。まずは無料相談などで「自分の場合はどうなりそうか」を聞いてみるのが一番の近道ですよ。
Q: シングルマザーだと、何か有利な点はありますか?
A: 直接的に「シングルマザーだから有利」という制度はありません。でも、児童扶養手当などを安定収入の一部として認めてもらいやすいですし、何より子供がいることで最低生活費が高く計算され、結果的に可処分所得が抑えられる可能性はあります。私の周りでも、そうした形で返済の負担が軽くなったママさんはいましたよ。
まとめ
個人再生で借金がいくら減るかは、3つの「ものさし」で決まります。特に可処分所得の計算は複雑で、一人でうんうん悩んでいても、なかなか正確な答えは出にくいものです。私もそうでした。
大切なのは、「私の場合はどうなるんだろう?」と思ったその時に、勇気を出して専門家のドアを叩いてみることです。私がお話ししたように、借金の額や財産の状況、家族構成によって、あなたにとって一番良い解決策は変わってきます。
この記事を読んで、「もしかしたら私も、今の生活を立て直せるかもしれない…」と少しでも希望が見えたなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。