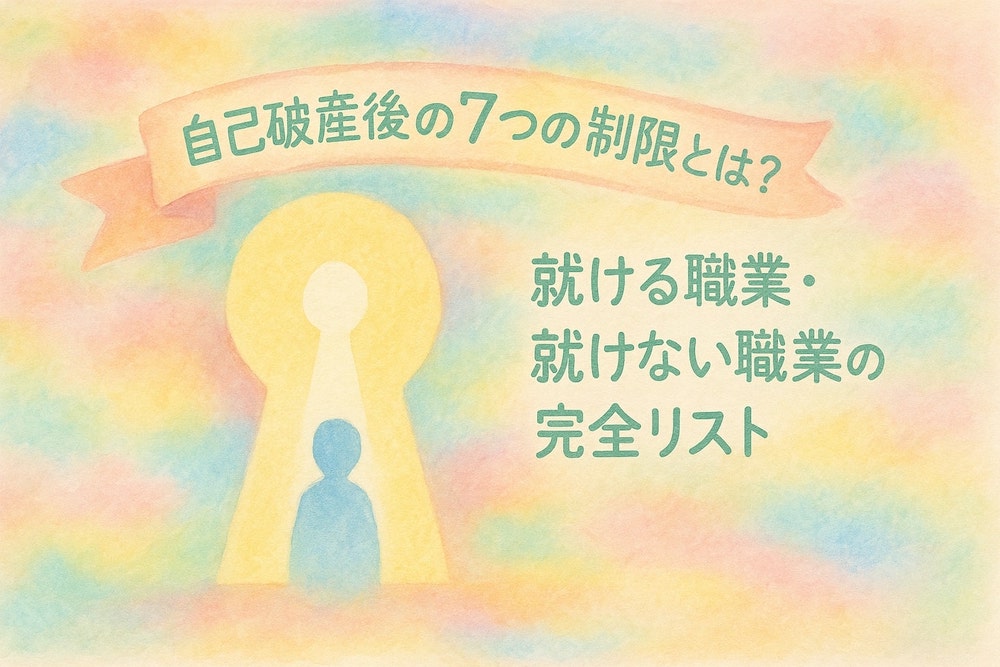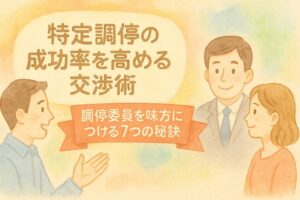「自己破産したら、人生オワコン。」
正直に言うと、25歳で2,000万円の借金を抱えた僕もそう思ってました。起業に失敗し、毎日鳴り止まない督促の電話に怯え、銀行口座の残高は三桁。そんな絶望的な状況から僕を救ってくれたのが「自己破産」でした。
結論から言うと、自己破産は人生のリセットボタンです。もちろん、いくつかの「制限」はあります。特に仕事への影響は気になりますよね。でも、安心してください。ほとんどの人は、今の仕事を続けられます。
この記事では、僕が実際に経験した自己破産後の7つの制限と、気になる職業制限について、僕自身の体験談を交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの不安はきっと軽くなるはずです。

【結論】自己破産後の7つの制限【元・破産者が全解説】
まず、自己破産でどんな制限があるのか、全体像を把握しましょう。巷で言われるデメリットを、僕の経験からリアルな影響度と合わせて7つに整理しました。
制限①:職業・資格の一時的な制限(今回のメインテーマ)
これが一番気になるポイントですよね。弁護士や警備員など、一部の職業には一時的に就けなくなります。でも、これは「手続き中の数ヶ月間」だけの話。ほとんどの会社員には影響ありません。後ほど詳しくリストで解説します。
制限②:ブラックリスト入り(約5〜7年間)
正直、職業制限よりこっちの方が生活への影響はデカいです。クレジットカードが作れない、ローンが組めないといった制限です。
僕も最初は不便でしたが、デビットカードやPayPayみたいなスマホ決済を駆使すれば、意外となんとかなります。これも人生のキャッシュフローを見直す良い機会だったりします。
制限③:価値のある財産の処分
持ち家や20万円以上の価値がある車などは、手放す必要があります。僕の場合は、事業で作った借金だったので、そもそも個人資産はほぼゼロ。失うものもなかったので、この点はあまり気になりませんでした。ちなみに、家族名義の財産は対象外です。
制限④:官報への掲載
国の新聞みたいなものに、名前と住所が載ります。「これで会社にバレるんじゃ…」とビビってましたが、一般の人が官報を毎日チェックすることはまずありません。僕もこれでバレたことは一度もないです。
ただ、闇金業者からDMが届くことがある、という話は本当なので注意が必要ですね。

制限⑤:郵便物の転送(管財事件の場合)
僕も経験したんですが、破産管財人が選任される「管財事件」の場合、手続き中は郵便物が一度管財人の弁護士事務所に転送され、中身をチェックされます。プライバシー的にちょっと嫌ですが、借金に関係ない手紙はちゃんと手元に届きますし、これも数ヶ月の辛抱です。
制限⑥:引越し・旅行の制限(管財事件の場合)
これも「管財事件」の場合ですが、手続き中に裁判所の許可なく引越しや長期の旅行はできません。財産隠しや逃亡を防ぐためですね。僕が申し立てた時は、弁護士さんから「2泊以上の旅行は事前に教えてください」と言われました。同時廃止という、より簡易な手続きなら、この制限はありません。
制限⑦:保証人への影響
これが精神的に一番キツいポイントかもしれません。もし借金に保証人がいる場合、あなたが自己破産しても保証人の返済義務はなくならず、その人に請求が行ってしまいます。
僕の場合は幸い事業融資の個人保証だけだったので、他人を巻き込むことはありませんでしたが、ここだけは事前にしっかりケアが必要です。
【完全リスト】自己破産で就けない職業・資格一覧
では、本題の職業制限について、具体的に見ていきましょう。あなたの仕事が当てはまるか、チェックしてみてください。
なぜ職業制限があるの?【サクッと解説】
簡単に言うと、「他人のお金や財産を扱う仕事」や「高い信頼性が求められる仕事」について、「この人は今、経済的に破綻状態ですよ」ということをクリアにするためです。
資格そのものが剥奪されるわけではなく、あくまで一時的な制限(欠格事由)に該当する、というわけです。
就けなくなる職業・資格リスト
主に以下の職業が該当します。リストにない職業、例えば一般的な営業職、事務職、エンジニア、医師、看護師、教員などは制限を受けません。
士業系
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士など
金融・信用系
生命保険募集人、貸金業者、質屋など
会社の役員(取締役など)
これは少し特殊で、法律上の欠格事由ではないんですが、民法の委任契約が終了するため、一度退任する必要があります。僕も会社の代表だったので、この手続きを取りました。
ただ、株主総会で承認されれば、すぐに再任することも可能です。
制限はいつまで?【人生のデバッグ期間は意外と短い】
この制限、一生続くわけじゃないので安心してください。期間は驚くほど短いです。
職業制限の期間は「破産手続開始」から「免責許可決定」まで
具体的には、裁判所に自己破産を申し立て、「破産手続開始決定」が出てから、「免責許可決定」が確定するまでの間です。この期間は、手続きの種類にもよりますが、だいたい3ヶ月〜6ヶ月程度。僕の場合は4ヶ月ほどでした。
この「免責許可決定」が確定すると「復権」といって、制限がすべて解除されます。
制限期間中の過ごし方【キャリアの再インストール戦略】
もし制限対象の職業に就いている場合、この期間は休職するか、制限のない部署へ一時的に異動させてもらうなどの対応が必要です。会社への説明は必須になりますが、自己破産したことだけを理由にクビにすることは不当解雇にあたるので、そこは安心してください。
僕はこの期間を「人生のデバッグ期間」と捉えて、今後のキャリアプランを練り直す時間に充てました。まさにキャリアの再インストールですね。
よくある質問(FAQ)
最後に、僕がよく聞かれる質問に答えていきます。
Q: 自己破産したら会社にバレますか?
A: 会社から借金をしている場合や、職業制限に該当する場合を除き、自分から言わない限りバレる可能性は極めて低いです。官報を毎日チェックしている会社はまずありません。ただ、退職金見込額証明書を会社に発行してもらう際に、何に使うのか聞かれて勘繰られる可能性はゼロではありません。
Q: 家族にどんな影響がありますか?
A: 家族が保証人になっていない限り、直接的な影響はありません。ただし、持ち家を失えば一緒に引っ越す必要がありますし、あなたが契約者の家族カードは使えなくなります。正直、隠し通すのは難しいので、誠心誠意話して協力を得ることが再起への近道だったりします。
Q: 選挙権はなくなりますか?
A: なくなりません。これはよくある誤解ですが、自己破産しても選挙権や被選挙権がなくなることは一切ありません。僕も普通に選挙に行ってます。
Q: スマホの契約はできますか?
A: 端末代金の分割払いはローン契約なので、ブラックリスト期間中は審査に通りません。ただし、通信契約自体は可能です。一括払いで端末を購入するか、手持ちの端末を使えば問題なく契約できます。
Q: 賃貸契約はできますか?
A: できます。ただし、信販系の保証会社を利用する物件は審査に落ちる可能性があります。僕も一度落ちました。不動産屋さんに正直に相談して、保証人がいればOKな物件や、信販系以外の保証会社を使える物件を探してもらうのがおすすめです。
Q: 資格試験の受験はできますか?
A: 受験自体は問題なくできます。ただし、宅建士などの制限対象の資格は、試験に合格しても免責許可が確定して「復権」するまでは登録ができません。
まとめ
自己破産後の7つの制限、特に職業制限について解説してきましたが、いかがでしたか?
正直、制限はゼロではありません。でも、そのほとんどは「一時的」なもの。特に職業制限は、多くの人には関係なく、対象者であっても数ヶ月の辛抱です。
僕自身、2,000万円の借金を自己破産でリセットしたからこそ、今こうしてWebマーケターとして働き、ブログで発信する生活ができています。借金で身動きが取れなくなっているなら、自己破産は人生を再起動させるための強力な選択肢です。
この記事が、あなたの「人生のピボット」のきっかけになれば、これ以上嬉しいことはありません。